主な活動
日本家庭教育学会TOP > 主な活動 > 家庭フォーラム
1997(平成9)年7月に、それまで刊行していた小冊子「家庭教育シリーズ」を発展させる形で創刊されました。現在までに28号を刊行しています。
家庭フォーラム 28号(2017年)
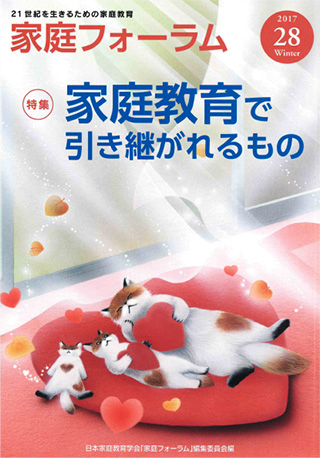
特集:家庭教育で引き継がれるもの
- 家庭で引き継いでいきたいもの(三砂ちづる)
- 親から子ヘ受け継いでいくもの(浜崎隆司)
- いのちの伝達と継承(石井雅之)
特別寄稿
- 日本社会の「多文化」化と家庭教育〜移民研究の視点から(明石純一)
連載
- 家庭・家族の俳句(第九回)(中田水光)
- 海外ルポ(第三回)カンボジア-カンボジアの女子サッカー支援(江田英里香)
- 家庭でできる自然療法の知恵(第三回)入浴の愉しみ(松本美佳)
クイズ
- 知っているようで知らない日本語
家庭フォーラム 27号(2016年)
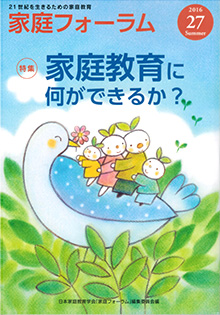
特集:家庭教育に何ができるか?
- 見方が変われば、関係が変わる―家庭教育におけるストレングス視点(山本智也)
- 心の居場所をつくる家庭は、子供の安全基地(伊藤美寿江)
- 家庭における「宗教」の教育(平良直)
連載
- 今、若者の世界で <不可解な流行語 フラグを立てて回収する>(編集部)
- 家庭でできる自然療法の知恵(第二回) <シンプルな慣習「白湯生活」>(松本美佳)
- 海外ルポ(第二回)<インドネシア――ゴトン・ロヨンと家庭教育>(江田英里香)
- 家庭教育師の広場 <精神疾患と子育てへの影響>(田光江美子)
クイズ
- 知っているようで知らない日本語
家庭フォーラム 26号(2015年)
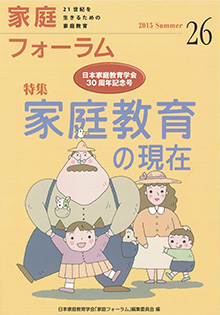
特集:家庭教育の現在
- 家庭教育の向上(中田雅敏)
- 文字によらない家庭内教育(西中研二)
- 「小さな物語」としての家庭教育(二川早苗)
連載
- 家庭・家族の俳句(第8回)(中田水光)
- 家庭教育師の広場 ふれ合う方の思いを大切に(吉水里江子)・「家庭教育師」としての取り組み(佐藤カヨ)
- 海外ルポ(第1回) カンボジア―プノンペンの発展と村の子どもたち(江田英里香)
- 家庭でできる自然療法の知恵(第1回) 正しい「呼吸」で元気になろう!(松本美佳)
クイズ
- 知っているようで知らない日本語
家庭フォーラム 25号(2013年)
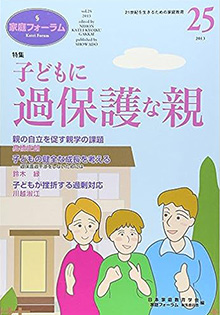
特集
- 過保護・過干渉 親の自立を促す親学の課題(髙橋史朗/明星大学教授)
- 子どもの健全な成長を考える(鈴木緑/家庭教育師・社団法人スコーレ家庭振興協会理事)
- 子どもが挫折する過剰対応(川越淑江/教育評論家)
連載
- おかあちゃんだより(第10回)
- 国際ボランティアの現場から(第16回)
- 家庭・家族の俳句(第7回)
家庭フォーラム 24号(2012年)

特集:子どもといっしょに体力づくり
- 子どもといっしょに体力作り(池端裕子・ハッピーファミリーグループ代表)
- 学校体育が目指しているもの(加藤純一・日本家庭教育学会常任理事・文教大学教育学部教授)
- 小学校での子どもといっしょに体力づくり(小原咲子・小学校教諭)
連載
- 家庭教育師の広場(第3回)
- おかあちゃんだより(第9回)
- 国際ボランティアの現場から(第15回)
- 家庭・家族の俳句(第6回)
家庭フォーラム 23号(2011年)
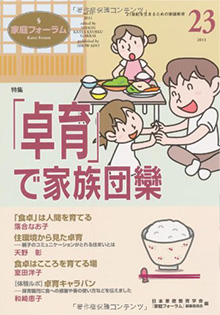
特集:「卓育」で家族団欒
- 「食卓」は人間を育てる(落合なお子・食空間研究家)
- 住宅環境から見た卓育(天野彰・株式会社アトリエ・フォア・エイ代表)
- 食卓はこころを育てる場(室田洋子・臨床心理士・聖徳大学児童学科教授)
- 【体験ルポ】卓育キャラバン(和崎恵子・NPO法人内閣府認証食空間コーディネート協会認定講師)
連載
- 家庭教育師の広場(第3回)
- おかあちゃんだより(第8回)
- 国際ボランティアの現場から(第14回)
- 家庭・家族の俳句(第5回)
家庭フォーラム 22号(2011年)
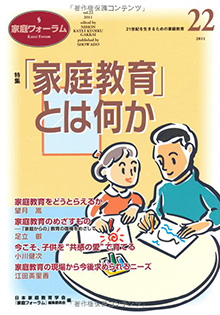
特集:「家庭教育」とは何か
- 「タイトル未定」望月嵩(日本家庭教育学会会長)
- 「家庭教育の現場から今後求められるニーズ」江田英里香(八洲学園大学生涯学習学部家庭教育専攻専任講師)
- 「家庭教育のめざすもの――『家庭からの』教育の復権をめざして」足立叡(淑徳大学副学長・教授)
- 「今こそ、子供を“共感の愛”で育てる」小川健次(家庭教育師・社団法人スコーレ家庭教育振興協会理事)
連載
- 家庭教育師の広場(第2回)
- 人をつくる教育(最終回)
- おかあちゃんだより(第7回)
- 国際ボランティアの現場から(第13回)
- 家庭・家族の俳句(第4回)
家庭フォーラム 21号(2010年)
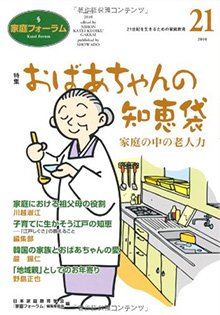
特集:おばあちゃんの知恵袋――家庭の中の老人力
- 「家庭における祖父母の役割」川越淑江
- 「子育てに生かそう江戸の知恵」編集部
- 「韓国の家族とおばあちゃんの愛」嚴錫仁(おむ・そぎん)
- 「「地域親」としてのお年寄り」野島正也
連載
- 家庭教育師の広場(新連載)
- 人をつくる教育(第7回)
- おかあちゃんだより(第6回)
- 国際ボランティアの現場から(第12回)
家庭フォーラム 20号(2009年)
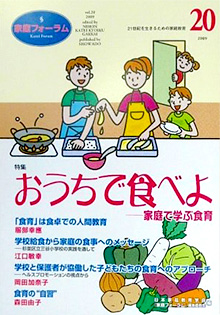
特集:おうちで食べよ〜家庭で学ぶ食育
- 「『食育』は食を通じた人間教育」服部幸應(医学博士・服部栄養専門学校校長)
- 「学校給食から家庭の食事へのメッセージ」江口敏幸(杉並区立三谷小学校栄養教諭)
- 「学校と保護者が協働した子どもたちの食育へのアプローチ――ヘルスプロモーションの視点から」岡田加奈子(千葉大学教育学部 教授)
- 「食育の‘自習’」森田由子(日本科学未来館 科学コミュニケーター)
連載
- 人をつくる教育(第6回)
- おかあちゃんだより(第5回)
- 国際ボランティアの現場から(第11回)
- 家庭・家族の俳句(第2回)
家庭フォーラム 19号(2008年)
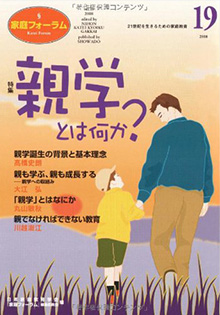
特集:親学とは何か
- 「親学誕生の背景と基本理念」高橋史朗(明星大学教授・親学推進協会理事長)
- 「親も学ぶ、親も成長する――親学への取組み」大江弘(PHP総合研究所)
- 「親学とは何か」丸山敏秋(社団法人倫理研究所理事長)
- 「親でなければできない教育」川越淑江(教育評論家)
連載
- 人をつくる教育(第5回)
- おかあちゃんだより(第4回)
- 国際ボランティアの現場から(第10回)
- 家庭・家族の俳句(中田雅敏・八洲学園大学教授)
家庭フォーラム 18号(2008年)
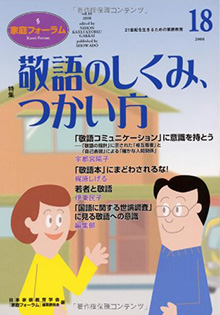
特集:敬語のしくみ、つかい方
- 「敬語本」にまどわされるな!/梶原しげる(アナウンサー)
- 「敬語コミュニケーション」に意識を持とう/宇都宮陽子(早稲田大学日本語研究センター非常勤講師)
- 若者と敬語/伊東民子(高校教師)
- 「国語に関する世論調査」に見る敬語への意識/編集部
連載
- 人をつくる教育
- おかあちゃんだより
- 国際ボランティアの現場から
家庭フォーラム 17号(2007年)
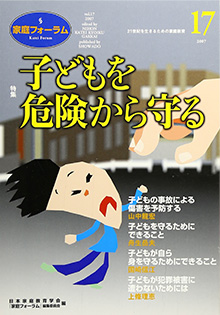
特集:子どもを危険から守る
- 子どもの事故による傷害を予防する 山中龍宏
- 子どもを守るためにできること 舟生岳夫
- 子どもが自ら身を守るためにできること 国崎信江
- 子どもが犯罪被害に遭わないためには 上條理恵
家庭フォーラム 16号(2007年)
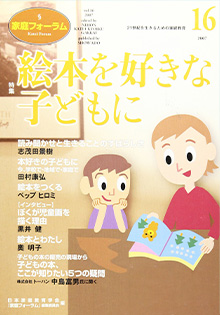
特集:絵本を好きな子どもに
- 読み聞かせと生きることのすばらしさ 志茂田景樹
- 絵本をつくる ベップヒロミ
- 絵本とわたし 奥明子
- ぼくが児童画を描く理由 黒井健
- 子どもの本の販売の現場から 中島富男
- 本好きの子どもに 田村康弘
家庭フォーラム 15号(2006年)
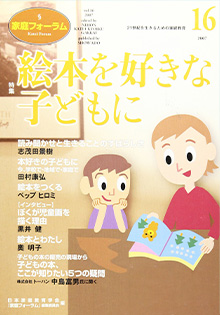
特集:箸と日本人
- 箸 日本人の心の拠り所 岸本明子
- 日本の伝統文化「箸の持ち方」 浜田駒子
- 箸と日本人 谷田貝公昭
- 「しつけ」は、「仕付け」で- はしとのかかわり合いを中心に- 神林照道
- 箸とは一生のおつき合い-箸づかいの基礎知識- 編集部/取材協力:高橋隆太